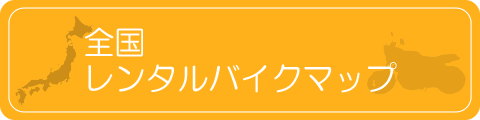バッテリーが上がったかも? そんなときの見分け方
エンジンがかからないとき、まず思い浮かぶのが「バッテリー上がり」。セルの回転が弱い、ヘッドライトがやけに暗い、インジケーターが無反応…そんな症状が出ていたら、その可能性はかなり高いです。
とくに最近のバイクはインジェクション車が主流。ECUや燃料ポンプなど、始動に必要な機能がすべて電気まかせになっています。つまり、バッテリーが完全に切れてしまうと、そもそも燃料を噴射する仕組みが動かず、エンジンがかかりません。
キャブレター車のように、「ちょっと電力が残ってれば押しがけできるかも」とはいかないのがインジェクション車の特徴なんです。
いざというときの対処法、どれを選ぶ?
では、出先でエンジンがかからないとき、どうすればいいのか。まずは「ジャンプスタート」。他のバイクや車のバッテリーと自分のバイクをブースターケーブルでつなぎ、一時的に電力を借りて始動する方法です。端子のつなぐ順番は間違えないように気をつけてくださいね。
最近はジャンプスターターという携帯型のバッテリーも市販されています。これがひとつあると、誰かに助けを求めなくてもエンジンがかけられるので、ツーリング派にはぜひ持っていてほしいアイテムです。最近のモデルはUSB出力も備えていて、スマホの充電にも使える優れもの。緊急用としてだけでなく、普段の装備としてもおすすめできます。
ちなみに「押しがけ」は、キャブレター車では有効な場合があります。ギアを2速に入れてクラッチを切った状態で押し出し、スピードがついたらクラッチをつなぐ。これで燃料と火花がそろえばエンジンはかかります。
ただし、インジェクション車ではバッテリーが生きていないと燃料すら噴射されません。つまり、押してもダメなときはダメ、というわけです。
バッテリーを守るために日ごろからできること
バッテリーのトラブルを防ぐには、日常の習慣が大事です。週1回でも30分ほど走るだけで、十分な充電になります。エンジンをかけるだけでは充電効率が悪いので、できれば実際に走るのが理想です。
しばらく乗らない時期には、マイナス端子を外しておくか、室内で保管するのがベスト。自然放電を防ぐことができます。湿度が高い場所だと、端子が腐食しやすくなるので保管場所にも少し気を配りたいところです。
あとは、電圧チェッカーで定期的に状態を確認しておくのもおすすめです。12.5Vを下回るようなら、そろそろ要注意。
バッテリーの寿命は一般的に2〜3年。セルの動きが鈍い、ライトがチラつくといった症状が出たら、思いきって交換を検討してもいいかもしれません。出先で困らないよう、バッテリーのケアも日々のメンテナンスの一部として意識しておきましょう。