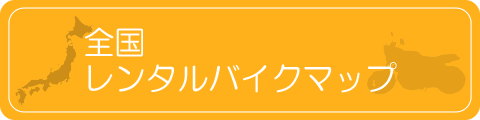信号のない横断歩道でもきちんと止まる長野県
JAF(日本自動車連盟)が2023年に実施した調査によると、信号機のない横断歩道でドライバーが一時停止する割合は全国平均で45.1%でした。
半数以上のドライバーが一時停止をしていないという、残念な結果になっています。
都道府県別でみると、一時停止する割合が最も低かったのは新潟県(23.2%)で、10台中わずか2台程度にとどまりました。
一方、最も割合が高かったのは長野県(84.4%)で、10台中8台が一時停止しています。
長野県は8年連続で全国1位を維持していますので、交通マナーの模範となる県といえるでしょう。
高い一時停止率の背景と課題―長野県の取り組み
長野県が高い一時停止率を維持している背景には、徹底した啓蒙活動があります。
例えば小学校低学年を対象とした交通安全教室では、長野県警の元職員が腹話術人形を使った指導を行っています。
講師は子どもたちに「横断歩道を渡るときは右手を高く上げて、運転手さんに見えるようにしましょう」と教え、「止まってくれたら『ありがとうございました』と言いましょう」と呼びかけています。
感謝の気持ちを伝えることで、運転手に「次も止まろう」という意識が芽生え、好い循環が生まれているのです。
さらに続けて「でも、横断歩道であっても必ず車が止まるわけではありません。止まるのを確認してから渡りましょう」と注意を促すことも忘れません。
というのも、長野県では一時停止率日本一だからこその課題を抱えているからです。
長野県警によると、2023年中に道路横断中の歩行者と車の事故は363件発生し、そのうち6割以上が横断歩道上での事故でした。
これは「停止率日本一」の意識が浸透し、横断歩道を利用する人が増えたためと考えられますが、その結果、横断歩道上での事故が増えるという皮肉な結果を招いているのです。
そこで長野県警は2024年から、横断歩道でのルール・マナー向上のための事業をスタートさせました。
交通安全事業を強化し、「一時停止率10年連続トップ」と「横断歩道での交通事故死者0人」を目指しています。
長野県警は「歩行者優先であるはずの横断歩道で、尊い命が失われる事故はあってはならない」と訴え、「ドライバーには『必ず止まる』という意識を、歩行者には『もしかしたら止まらないかもしれない』という注意を常に持ってほしい」と呼びかけています。
そのためには、ドライバーと歩行者が互いに目を合わせて安全を確認する「アイコンタクト」が重要だということです。
また長野県警は、地元のお笑いコンビ「こてつ」を起用した動画を制作し、横断歩道での一時停止を呼びかけるなど、さまざまな取り組みを行っています。
長野県に限らず、車やバイクを運転する方は、信号のない横断歩道での一時停止を心掛けましょう。